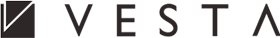住宅を取得する際に気になる事の一つが「住宅の保証」です。
住宅の保証には、大きく分けて2つ“10年以上の長期の保証“と“1~2年の短期の保証”があります。
今回は新築住宅(築1年未満)の物件を対象にした保証についてお話しします。
短期の保証
売主が自主的に提供する保証です。
そのため会社により少しずつ違いがありますが、一般的には、住宅保証機構(国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人)が示す基準が利用されており、弊社でもこの基準を採用しています。
例えば、
ガスの配管については、保証期間2年間で、「配管は接続・指示不良、腐食、破損等が生じてはならない。」が保証基準とされています。
ほかに、
建具、ガラス工事については、外部及び内部建具を対象に2年間の保証期間で、「建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはらない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。」とされています。
このように箇所ごとに1~2年の品質性能基準が決められていますが、先述の通り売主の会社により異なることもありますので、契約前に保証書を確認することをお勧めします。
長期の保証
長期の保証については、次のような法律で定められています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)2000年4月1日施行
通称「品確法」と言われています。
この法律では、住宅性能表示制度や新築住宅の瑕疵についてその担保期間10年の義務化が定められています。
「瑕疵(かし)」とは : 本来あるべき、約束されているはずの機能や品質などが備わっていない状態のこと。いわゆる欠陥と同じような意味合いがあります。
つまり住宅として最低限の性能が確保されていなければ瑕疵とみなされます。
ただし、構造計算等に不備がなく役所の確認を得た設計図書通りにつくられている場合や、工事途中に互いに了解を得て変更されたものについては瑕疵にあたりません。
また対象となるのは、“構造上主要な部分”と“風雨の侵入を防ぐ部分”です。
構造上主要な部分 : 柱、梁、耐力壁、基礎、地盤などの構造躯体
風雨の侵入を防ぐ部分 : 外壁、屋根、窓などの開口部 など
瑕疵担保期間10年の義務化が定められたのち、2005年に起きたのがマンション耐震偽装問題。
偽装自体も大きな問題となりましたが、ここでもう一つ問題となったのが、瑕疵担保責任を負う会社にその能力が無くなり、多くの消費者が泣き寝入りしてしまったことです。
これを受けて、品確法を補足する立ち位置で作られたのが、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」2009年10月1日施行
略して「住宅瑕疵担保履行法」です。
この法律で、新築住宅の売主に対して“専用の保険に加入”するか“保証金を法務局に供託”することが義務づけられ、施工会社が倒産などで瑕疵担保責任が果たせない状態の時、消費者は保険会社や供託所から保険金などを受けとることができるようになりました。
ちなみに弊社では、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人 株式会社日本住宅保証検査機構(通称JIO(ジオ))の住宅瑕疵保険に加入しています。
JIOのウェブサイトはこちら
以上が、新築住宅に関する保証の内容です。
<補足>
今回紹介した品確法による長期保証では、中古住宅は対象外ですが、宅建業法上、売主が宅建業者の場合に限り、新築・中古に関わらず最低2年間はその責任を負うことになります。
また、最近では中古住宅向けの1~5年間の保証が整備されつつあります。中古物件をご検討される方はぜひ調べてみてください。