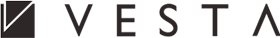関東の梅雨入りから3週間が過ぎ、やっと梅雨らしい天気になってきました。梅雨入りしてから「さぁ来い!」と気合を入れていたので、ちょっと拍子抜けしてしまいました。
どうやら梅雨前線が本州から南に逸れたところで停滞していたんだとか。実は10年前にも梅雨入りしたのちに、改めて梅雨入り日が後ろ倒しに修正されたことがあったそうです。
こんなちょっとした気候や環境の変化を見ていても、自然災害に係わる火災保険がこまめに改定されていくのにも頷けますし、定期的な見直しも大事ですね。
さて、という事で前回に続き“火災保険”に関して書いてみます。
今回は賃貸物件を借りる際の火災保険です。
賃貸の火災保険
賃貸物件では、建物に関してはオーナー様が保険に加入しているので、借主は自身の家財に保険をかける必要があります。
基本的な家財の補償対象・内容は所有物件と同じです。(前回のブログ参照)
また、賃貸借契約には原状回復義務があり、退去時には入居時の状態に戻す必要がありますが、万が一、部屋に何かしらの損害を出してしまった場合、借主はオーナー様への損害賠償責任を負うことになります。
賃貸の家財保険では、このような事態に備えることができます。
補償内容は、保険会社によって所有物件と同じ場合と、賃貸専用のプランがある場合とあるので、前者の場合は賃貸に必要な特約を付けましょう。
賃貸にお住まいの方向けの特約には、「借家人賠償責任補償特約」や「修理費用補償特約」があります。
「借家人賠償責任補償特約」は、オーナー様に対し法律上の損害賠償責任を負う事象が発生した際に、その損害を補償するもの。
「修理費用補償特約」は、賃貸借契約に基づいて、自己負担にて修理を行った際の費用を補償するもの。
賃貸専用プランの場合、これらの賠償責任補償や修理費用補償の内容がメインとなり、より利用しやすい内容になっています。ある保険会社では、賃貸から賃貸への引越しの際、日本国内であれば解約・再加入の手続きをせず保険を継続することができるものもあります。
また、これらの特約やプランには、オーナー様との間に入ってくれる「示談交渉サービス」が付いている場合と、無い場合とありますので、これもチェックしておくと良いでしょう。
事故発生時の手続き
では、実際に事故が発生した際、どのような流れで保険金が受け取れるのでしょうか。
あらかじめ知っておくと、万が一の時、手続きがスムーズに済みます。
事故が発生したら、何よりもまずは警察や消防、救急へ連絡し、損害の拡大を抑えましょう。また、盗難などの場合は、できる限り周辺の物に触れず、現状維持に努めます。
保険金請求手続きに必要となりますので、担当の官公署名と担当者の名前を控えておきましょう。
<事故発生の連絡>
事故からなるべく早いうちに、保険会社もしくは契約した際の代理店へ連絡します。
この際、以下のような内容を確認されますので、あらかじめメモに書き出しておくと便利です。
- 契約書の名前
- 保険証券番号
- 事故発生の日時・場所
- 届出官公署名・担当官名
- 修理先(業者名・電話番号)
- 事故後の連絡先 などなど
<保険会社と打合せ・調査>
連絡後、保険会社の担当者から折り返しの連絡が来て、事故の発生原因や被害状況などを確認します。
必要に応じて現場で立ち合いを行う場合もあります。
<保険金請求書類の作成・提出>
調査の結果、保険金額が決定し、手続きへ進みます。
渡された書類へ記入し、ほか指示された必要書類(住民票や身分証明書など)を準備します。必要書類は事故の種類や程度によって異なりますので、担当者に確認しましょう。
<保険金の受取り>
保険会社が書類を確認後、問題がなければ保険金が支払われます。
以上が大まかな流れです。
あくまでも一例ですので、担当者の指示に従って手続しましょう。
また、万が一の時に備えて、保険会社や代理店の連絡先や問合わせ先を分かりやすいところに控えておくこともお勧めします。